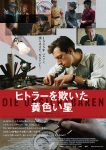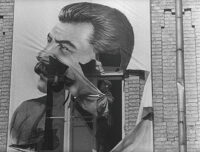他の都道府県と違い、政治家と県民がお互いを信頼している関係がある…『太陽(ティダ)の運命』佐古忠彦監督に聞く!

政治的立場は正反対でありながら、国家権力と闘ったふたりの沖縄県知事、大田昌秀と翁長雄志の姿を通して、この国の現在地を探る『太陽(ティダ)の運命』が5月2日(金)より関西の劇場でも公開される。今回、佐古忠彦監督にインタビューを行った。
映画『太陽(ティダ)の運命』は、『米軍が最も恐れた男 その名は、カメジロー』の佐古忠彦監督が、それぞれ国と激しく対峙した2人の沖縄県知事の姿を通して、沖縄現代史に切り込んだドキュメンタリー。沖縄本土復帰後の第4代知事である大田昌秀さん(任期:1990~1998年)と第7代知事の翁長雄志さん(任期2014~2018年)は、政治的立場は正反対でありながらも、ともに県民から幅広い支持を集め、保革にとらわれず県政を運営した。大田さんは1995年に軍用地強制使用の代理署名拒否、翁長さんは2015年に辺野古埋め立て承認の取り消しを巡って国と法廷で争い、民主主義や地方自治のあり方、そして国の矛盾を浮き彫りにした。彼らの人生に関わった多くの人々の証言を交えながら、その人間的な魅力にも光を当て、それぞれの信念に生きた2人の不屈の闘いを描きだす。タイトルの”ティダ”は沖縄の方言で太陽の意味で、古くは首長=リーダーを表した言葉である。
沖縄に通い始めて四半世紀以上になる佐古監督。2022年、沖縄本土復帰から50年を迎えた夏に「沖縄の民意を示す”沖縄県知事”が国との対応に苦悩する姿を描くことで日本の問題を浮き彫りにできないか」と構想。玉城デニー知事までの8代の知事の中で、本作では、第4代知事の大田知事と第7代知事の翁長知事にスポットをあてているが「政治的立場は正反対でありながら、翁長さんが大田さんと同じようなことを発言するようになった。元々どのような関係であるか理解していたので、どうしてこうなってきたんだろう。それらを紐解きたい」といったことが念頭にあった。
今回、知事の視点を通した現代史を浮き彫りにしようとしていく中で、本作は、琉球放送のアーカイブ映像を中心にしながら、インタビュー取材との組み合わせによって構成されており「琉球放送との共同制作では、まずRBC(琉球放送)の映像ライブラリーに籠って、30年の映像を総浚いしていく。そこから、どこを抽出して、どのように組み立てていくか。そして、どのような人に証言をしてもらうか、と考える作業があった」と説く。その証言者の一人が大田知事時代の知事公室長だった粟国正昭さん。橋本総理から電話があった時、大田さんの隣にいた人物だ。まるで、当時の光景が浮かぶような証言をしてくれたという。また、大田さん、翁長さん双方をよく知る稲嶺惠一さんは、沖縄県知事としての苦悩も語ってくれた。「稲嶺さんは、ストーリーテラーの存在になっていただいた」と明かす。
『太陽(ティダ)の運命』というタイトルについては「太陽は、沖縄の象徴的なもの。ここでは、沖縄の言葉で”ティダ”と呼ばせたい」と考えた。そして、”ティダ”は、その昔、リーダーを表す言葉でもあった。また、冒頭で取り上げる初代知事の屋良朝苗さんの復帰の日の日記には”運命”という言葉が多々あり「知事たちは、沖縄の運命にどのように向き合ってきたのだろうか」という思いからこのタイトルに行き着いたという。
既に、沖縄の桜坂劇場では3月22日(土)より先行公開されている。お客様からは「この作品を作ってくれて、ありがとう」「気持ちを代弁してくれてありがとう」といった声をかけられた。「涙を流しながら御覧になっている方も多い。この2人と同じ時代を生きて、悔しさや悲しさを共有し、事象は今も続いている。 つまり、皆が当事者だと思うんです。当事者としての沖縄の人ならではの特別な感情に触れたような気がする」と話す。
これまでに、瀬長亀次郎さんや島田叡さんにスポットを当て、沖縄の歴史を映し出すドキュメンタリーを手掛けてきた佐古監督。「政治のリーダーを描いているんですけど、政治家をヒーローにしているのではない。実は、そこを通して見えてくるのは沖縄の人たちの歩みです」と語っている。
映画『太陽(ティダ)の運命』は、関西では、5月2日(金)より京都・烏丸の京都シネマ、5月3日(土)より大阪・十三の第七藝術劇場、5月10日(土)より神戸・元町の元町映画館で公開。

- キネ坊主
- 映画ライター
- 映画館で年間500本以上の作品を鑑賞する映画ライター。
- 現在はオウンドメディア「キネ坊主」を中心に執筆。
- 最新のイベントレポート、インタビュー、コラム、ニュースなど、映画に関する多彩なコンテンツをお伝えします!