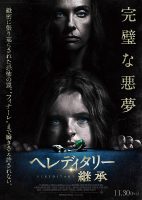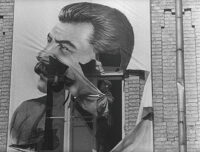彼女たちが残した行動を伝えなくてはいけない…『黒川の女たち』松原文枝監督に聞く!

1945年の関東軍敗走後の満州で、岐阜県から渡った黒川開拓団が、生きて日本に帰るために払った犠牲に関する証言を集めたドキュメンタリー『黒川の女たち』が7月12日(土)より全国の劇場で公開される。今回、松原文枝監督にインタビューを行った。
映画『黒川の女たち』は、戦時下の満州で黒川開拓団の女性たちに起きた「接待」という名の性暴力の実態に迫ったドキュメンタリー。1930~1940年代に日本政府の国策のもと実施された満蒙開拓により、日本各地から中国・満州の地に渡った満蒙開拓団。日本の敗戦が濃厚になるなか、1945年8月にソ連軍が満州に侵攻し、開拓団の人々は過酷な状況に追い込まれた。岐阜県から渡った黒川開拓団の人々は生きて日本に帰るため、数えで18歳以上の15人の女性を性の相手として差し出すことで、敵であるソ連軍に助けを求めた。帰国後、女性たちを待ち受けていたのは差別と偏見の目だった。心身ともに傷を負った彼女たちの声はかき消され、この事実は長年にわたり伏せられることになる。しかし戦争から約70年が経った2013年、黒川の女性たちは手を携え、幾重にも重なる加害の事実を公の場で語りはじめた。そんな女性たちのオーラルストーリーを、『ハマのドン』の松原文枝監督が丁寧に紡ぎ出す。俳優の大竹しのぶさんが語りを担当した。
敗戦直後の満洲で性暴力が起きていたことについて、松原さん自身も知らなかったようだ。実際、2017~8年頃には地元紙に書かれている程度だった。2018年8月、93歳の佐藤ハルエさんが、岐阜県の岐阜市民会館で、自身が性接待にあったことを証言し、朝日新聞の全国版で社会面に掲載され、松原さんも「こんな女性がいるんだ」と知ることに。「93歳という御高齢だから話せるようになった」という声も聞いたが「歳がいったから、といっても…そういった話は家族にも言わず最後まで隠し通そう、と考えてしまう。よくぞ話していただいたな」と驚いた。また、記事の横には、佐藤ハルエさんの写真が掲載されており「今こそ伝えなくてはいけない、という意思の強さを感じた。彼女の表情に惹きつけられた。この人はどういう人なんだろう」と興味津々。「公の場で、顔も実名も出し、自身が性暴力を受けたことを語るのは相当な覚悟が必要なこと」と察しながら、取材出来る機会があるか、遺族会の方に伺ってみることに。最初は「ありません」といった反応だったが、2018年10月に連絡があり、地蔵菩薩の横に碑文が建立される際に佐藤ハルエさんがいらっしゃることを知り、取材することを決めた。
取材では、佐藤ハルエさんの場合、御家族も知っていたこともあり、坦々と話してもらい「弱音を吐かない方だった。自分の中で一線を引いているようだった。自分が傷つかない範囲で事実をしっかりと伝えようとしている」と受けとめている。一方、安江玲子さんの場合、御家族に知らせておらず、時間や場所の制約がある中で、ご本人が了解の上で取材を受けてもらった。また、黒川開拓団遺族会会長の藤井宏之さんからは「女性達の思いを受けとめ、社会にしっかりと伝えていかなくてはいけない」といった思いがあることが分かり、しっかりと伝えるメディアに対しては丁寧に対応してもらっている。松原監督も取材をするにあたり「この言葉を使うと傷つけるんじゃないか」と気にしたり「どう思ったか、なんて…そんなこと聞かないでよ」と言われたりするんじゃないか、と心配だった。「リアリティを以って当時のことを伝えるにあたり、当時の気持ちも含めて聞きたい。相手を傷つけることになるかもしれないし、当時を思い起こさせることになる。彼女たちにとって失礼なことを言っていたり、場合によっては傷つけたりすることも当然あり得る」と十分に神経を使い、質問するときも「大丈夫かな」と様子を伺いながら、十分に考えながら取材をしている。とはいえ、どれだけ聞くことができる分からない中で「話せるところまで話していただけたら良いな」という心持ちで臨んだ。佐藤ハルエさんとの取材は回数を重ね、3回目あたりからご自身の気持ちを吐露していただいた。「ご自身が当時に思ったこと、怒りもあったし、辛さもあったし、悲しさも計りしれないと思うんです。そういった言葉を使うことすらも、やりたくないことだった。気持ちを聞くことも、ままならなかった」と思い返しながら「当時の出来事をなるべくリアリティを以って語っていただくと伝わってきます。一方で、語ることによって自身を傷つけることでもあります。こちらが聞くことさえも、彼女達をわざわざ傷つけることをやっていることにもなりかねない」と実感している。
2019年6月には、安江玲子さんに取材した。首から下だけでの撮影となり、話しやすかった側面もあったようだ。当時について、リアリティある状況の説明や気持ちを詳しく話していただいた。取材を進めていく中で変化していることを見受けられ「こうやって人間は自分自身を取り戻していく、尊厳を回復していくんだ」ということを目の当たりにする。その後、2024年1月に佐藤ハルエさんが老衰のため99歳でお亡くなりになり「彼女たちが残した行動を伝えなくてはいけない。映画という形で残したい」という気持ちに突き動かされた。その時、本作の最後をどのように締め括るか、といったことまでは考えられなかったが「伝えていくことが生きている者の務めでしょう、というハルエさんの最後の言葉は、映画の最後に使いたいな」と望んだ。
一方、黒川開拓団遺族会の男性に取材した際には「なにかを残していかなきゃいけない」という気持ちを持った方が多く、世代が変わったことによって、向き合う姿勢を感じ、前向きに対応してくれたことに感謝している。また、御家族の方々にも取材しており「お孫さんは、おばあちゃんにものすごく理解ある。彼女たちが語る、ということは容易ではないことを理解し、尊敬の念を持っている」と受けとめた。「彼女たちが気迫を以って伝えようとしていることで、自分たちがいろんなこと言われるリスクがある。それでも、戦争によって起きたことを残していかなくちゃいけない、という強い意志でやっている姿を見て、それは普通にできることじゃない、と分かっている」と伝わってきて「彼女達の行動や、その力強さを見て、大事にしたい、理解する、という気持ちになるんだ、と思うんです。お孫さん達にも繋がり、その思いは埋め込まれている」と理解していく。なお、作中には、この出来事について高校で教えている教諭の姿が映し出される。松原監督は、シンポジウムで出会い、許諾を得て取材に伺った。教諭自身で考え、先行研究等の書物を借りて読んだ上で、独自のプリントを作成して生徒達に教えており「自身で見聞きし、それらを歴史の中の文脈で捉え、さらにその構造についても考えた上で、生徒達に教えているのは、救いがある」と印象に残っている。編集時には「”昔のことだ”と受けとめられちゃうと嫌だな。今の時代に繋げたい」という意向があり「お孫さんを通して、引き継がれているものを描くことが出来る」と考えたり「今取り組んでいることを知ったので、それらを撮って作品に入れよう」と取り組んだりしていった。これらは、最初の企画段階から構成を考えた上で盛り込まれたことではないが、現代に至るまでの経緯を納得した上で製作されている。
完成した作品は、マスコミ向け試写が開催されており「女性が多いんですけど、彼女たちの痛み、彼女たちが起こそうとしたものに対する共感みたいなものがものすごくある」と受けとめており「彼女たちを、映像として残してくれて本当に良かったです」といった反応を届けてもらった。なお、今後については模索中ではあるが「強いものに抗い、突破していく力のある人たちを追いかけていければ」と思っており「原発のエネルギーの問題、憲法、民主主義の土台を、誰かを通して描くかどうか、といったことが関心のあるテーマではありますね」と語った。
映画『黒川の女たち』は、7月12日(土)より全国の劇場で公開。関西では、7月12日(土)より大阪・難波のなんばパークスシネマや京都・三条のMOVIX京都、7月18日(金)より京都・烏丸の京都シネマ、7月19日(土)より大阪・十三の第七藝術劇場や神戸・元町の元町映画館で公開。

- キネ坊主
- 映画ライター
- 映画館で年間500本以上の作品を鑑賞する映画ライター。
- 現在はオウンドメディア「キネ坊主」を中心に執筆。
- 最新のイベントレポート、インタビュー、コラム、ニュースなど、映画に関する多彩なコンテンツをお伝えします!