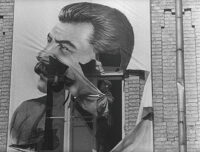もしかしたら穴水町も町長も本質的に変わるかもしれない…『能登デモクラシー』五百旗頭幸男監督に聞く!

能登半島中部の石川県穴水町で手書きの新聞を発行する活動を通して、限界集落の人々の生活を見つめたドキュメンタリー『能登デモクラシー』が5月17日(土)より全国の劇場で公開される。今回、五百旗頭幸男監督にインタビューを行った。
映画『能登デモクラシー』は、『はりぼて』『裸のムラ』といった政治ドキュメンタリー作品を手がけてきた五百旗頭幸男監督が、能登半島の中央に位置する石川県穴水町を取材したドキュメンタリー。人口が7000人を下回り、若者と高齢者の数がともに減りゆく「人口減少の最終段階」に入った石川県穴水町。元中学校教諭の滝井元之さんは2020年から手書きの新聞「紡ぐ」を発行し、利益誘導型の政策や町の未来に警鐘を鳴らし続けてきた。五百旗頭監督ら石川テレビのクルーたちは、市井からのまなざしにローカルメディアの存在意義を重ねながら、惰性と忖度がはびこる役場と町議会のいびつな関係を浮き彫りにしていく。そして2024年の元日、能登半島地震が発生。カメラは思わぬ事態に見舞われた町と人々の営みをつぶさに見つめる。やがて五百旗頭監督は、まことしやかに囁かれる穴水町最大のタブーに切り込んでいく。
前作『裸のムラ』の舞台でもあった石川県穴水町。作中に登場する主人公の1人である中川生馬さんからも冗談交じりながらも町民視点で「次は、穴水町政でドキュメンタリーを作ってくださいよ」と言われていたそうだ。とはいえ、その視点は辛辣で、自身のブログでも批判的である。それは、本作における滝井さんと通じるものがあった。だが、滝井さんのようにコンスタントに町役場や町議会に提言する方はいない。
そこで、まずは、石川テレビでのドキュメンタリー番組制作を目的に穴水町での取材に取り組んでいった。とはいえ、当初は、住民の視点で穴水町にある問題点を指摘する人物が見つからず。あえて町長に密着する取材をしていく中で、問題点をあぶり出す手法も検討。最終的には、そこから町長の中にある本質的な部分を探っていき、なんらかの問題を追求しようとしたが、前作『裸のムラ』の影響により、五百旗頭さんへの警戒心があることを考慮し、現実的ではないと認識した。そこで、監督と町長側との緊張関係が映像に溶け込むような状態を維持しながら、町民側のキーマンを探していく中で、滝井さんを発見。滝井さんが発行する新聞『紡ぐ』を全て読んだ時に「これは、いける」と確信した。
その後、取材を進めていく中で、2024年の元旦に能登半島地震が発生。五百旗頭さんは翌日から1人で連日の如く現地取材を行っていった。その中で撮影素材も多くなっていき、5月に放送される番組まで編集を終える必要があり、物理的な作業量の多さもあり大変だったようだ。とはいえ「今は苦しいな、と感じたことはない」と自負している。しかし、今作の場合、途中で懐疑心を抱かざるを得ないシーンが挟み込まれており「それぞれのシーンを全体の構成の中でどのようにして有機的に繋げることができるか、最終的にどのような取材を行っていくか、と頭を相当に悩ませました」と葛藤があったことも明かした。「地震が起こっていなければ…過疎の町においては民主主義も壊れていく中で、コンパクトシティ政策によって町中に次々と様々なものが集められ、結果的に周辺部や限界集落は取り残されていく。この視点元にして、滝井さんを通して問題点を色々指摘していく」といった番組の構想もあったが「震災が起こったことにより、翻って、限界集落周辺部のたくましさが見えてきた。水の供給が途絶えてしまったら、昔使っていた水源を自分達で探しに行ったり、水が通るようになっても壊れている配管を自分達で修理したり、とたくましかった」と挙げ、震災がなければ気づけなかった部分をしっかりと映し出していく。そして、震災後の民主主義再生に向けた変化が少しずつ見えるようになり「もしかしたら穴水町は変わるかもしれない」と感じられるような番組としてまとめた。
なお、2024年5月、ドキュメンタリー番組「能登デモクラシー」が放送される際には「滝井さんに対する攻撃、誹謗中傷、否定的な意見が出てくるかもしれない」と鑑み、滝井さんに対しても「攻撃や誹謗中傷を受けた際には、すぐに連絡ください。僕、すぐ取材に行きます」と連絡している。これは「謗中傷してきた人も含めて取材したい。そうすれば、それが誹謗中傷の抑止力にもなるかな」といった意図もあったが、放送後、滝井さんへの攻撃などはなく、石川テレビに対しても一切なかった。滝井さんをさらに応援する声があり「穴水町の人達は知っていたけど、交流センターについては町民の大半が多くを知らなかった。だからこそ、よく教えてくれました。教えてくれてありがとう」といった声もあったようだ。さらには、穴水町の内外からカンパを携えて滝井さんの自宅を訪れる方が現れ、さらに支援の輪が広がった。これは、五百旗頭さんらも驚いており「嬉しい誤算だった。実際に反応を見せつけられると、映画にする意義もあるかな、と感じました。穴水町だけではなく、全国に広げる意義がある」と気づかされていく。当初は、あくまでドキュメンタリー番組の制作までを予定していたが、想定外の反響を受け、あらゆる要素を含めて取材し「最終的に映画としてしっかりとまとめ上げることができた」と手応えを感じている。
本作では、ドキュメンタリー番組が放送されて以降に変化していく穴水町の姿も映し出していく。この変化の要因について、五百旗頭監督は、滝井さんの地道な活動の積み上げを挙げた。「滝井さんの活動がなければ何も成立しなかった。その上で震災があり、町民の危機意識が高まった。それまでは町長に対して直接意見を言う人がいなかった。だが、震災後は町議会や住民説明会などで意見を表明する人が増えた」と捉えると共に「番組の放送によって、滝井さんに対する信頼感がさらに高まった。ようやく議員側にも意識の変化が少しだけ見られるようになった」と受けとめている。そして、震災後の一番大きな変化として、吉村光輝町長が決定的に変わったことを挙げた。震災後に馳浩知事が穴水町を視察した時、五百旗頭さんは能登の切り捨てについて質問した際に、吉村町長は「人の少ないところに道路や建物を建てないことになれば、1人の命の価値に優劣をつけることになるからナンセンスだ」と応えている。この発言について、五百旗頭さんは「コンパクトシティ政策を掲げてきた町長にとってはすごく矛盾する発言。これまでの自身の言動や政治的なスタンスに対する刃でもある。それを自分達が能登ごと切り捨てられる立場になったら、自分達が今まで周辺部を切り捨てる立場だったけど、自分達が切り捨てられる立場になった時に初めて出た本音だ」と解釈しており「町長は少し変わってきたな」と感じられた。「それまでには感じられなかった首長としての責任感や危機意識をようやく見ることができた」といった象徴的なシーンであり「その後に取り組んでいる復興に向けた計画作りの部分でも変わったな、と目に見えるように分かった」と実感している。
また、『はりぼて』『裸のムラ』には、映し出される騒動について、滑稽なシーンと受けとめられるような劇伴の音楽が添えられており、本作においても一風変わった劇伴の音楽があった。五百旗頭監督としては、具体的な依頼はしておらず「完成前のラフな段階で映像を見てもらった上で作曲してもらっている。あくまでその結果でしかないです。そして、音楽プロデューサーの矢﨑裕行さんが出てきた曲を元に色々アレンジをして、シーンごとに合うように作っていってくれた」と話す。本作には、「穴水ラプソディー」というメインテーマの楽曲があり「音楽プロデューサーとしても『こういう曲調で来たか』と意外だったみたいですね」と振り返りながら「繋いだ映像をどのように音楽の専門家が解釈するか。最初の鑑賞者としてインスパイアしてもらいながら、ちょっとここに合わないな、と変えてもらうことはあります」と明かした。
当初、『能登デモクラシー』というタイトルについて「”民主主義”や”デモクラシー”といった直接的な表現を嫌う人もいる。観客が逃げていく恐れもある。あまり使いたくなかった」と打ち明けながらも「能登半島地震が発生し、能登が切り捨てられかねない、という懸念を持っている町民の方々が沢山いた。やはり”能登”をしっかりと打ち出すべきかもしれない」と検討。取材を始めた頃は、民主主義を否定するかのような光景を見せつけられたこともあり「”ノットデモクラシー”でいこう。”Not Democracy”であり”No To Democracy”。能登はローマ字で”Noto”。だからこそ、デモクラシーは入れようか」と考え直した。『田舎デモクラシー』や『過疎デモクラシー』といったタイトルを考えたこともあったが「やはり”能登”というキーワードが必要だ。”デモクラシー”に関しても、常識や倫理が失われていくこの時代にあって、あえてド直球でいった方がいい」と熟考し、『能登デモクラシー』というタイトルに落ち着いている。
現在の穴水町について、五百旗頭監督は「民主主義再生への芽吹きは見えてきたけど、実態として、何かが大きく変わった、とかはないと思います」と正直に話し「今後に懸かっているんじゃないでしょうか。だから、今後もしっかりと取材し、その上で期待している、と町長に伝えた」と真摯な姿勢を表す。現段階では「吉村町長が本質的に変わった、とは思えていない。だからといって、もうこの人は駄目だ、と言って切り捨てない。もしかしたら吉村町長も穴水町も本質的に変わるかもしれない」と考えており「だからこそ、希望が見出せるような作りにするため、余白を残している」と語った。
映画『能登デモクラシー』は、5月17日(土)より全国の劇場で公開。関西では、5月17日(土)より大阪・十三の第七藝術劇場、5月23日(金)より京都・烏丸の京都シネマ、6月14日(土)より神戸・元町の元町映画館で公開。

- キネ坊主
- 映画ライター
- 映画館で年間500本以上の作品を鑑賞する映画ライター。
- 現在はオウンドメディア「キネ坊主」を中心に執筆。
- 最新のイベントレポート、インタビュー、コラム、ニュースなど、映画に関する多彩なコンテンツをお伝えします!