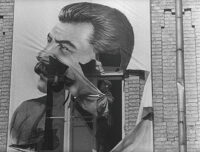『はだしのゲン』が持っている熱量を世の中に知らせなきゃいけない…『はだしのゲンはまだ怒っている』込山正徳監督に聞く!

戦後80年を迎えてもなお、ウクライナをはじめとした戦火が続き、消えない核の脅威への怒りや悲しみを『はだしのゲン』を通して描く『はだしのゲンはまだ怒っている』が11月21日(金)より関西の劇場でも公開。今回、込山正徳監督にインタビューを行った。
映画『はだしのゲンはまだ怒っている』は、漫画家の中沢啓治さんが自身の被爆体験をもとに描き、反戦・反核を訴える漫画として読み継がれてきた『はだしのゲン』を題材に取り上げたドキュメンタリー。原爆で被爆した主人公の少年ゲンが、家族を失い、貧困や偏見に苦しみながらも力強く抜く姿を描いた『はだしのゲン』。週刊少年ジャンプでの連載が始まった1973年から半世紀、25ヶ国で翻訳出版され世界中で読まれ続けてきたが、近年は”描写が過激”、”間違った歴史認識を植え付ける”と学校図書館での閲覧制限を求める声が上がったり、広島市の平和教材から消えたりするなど、大きな議論を呼んでいる。『はだしのゲン』が人々をここまで熱くさせるのはなぜなのか。本作では、作品誕生から現在を見つめることで、世界に溢れる怒りや悲しみ、優しさを映し出していく。2024年8月放送のBS12スペシャル「『はだしのゲン』の熱伝導 原爆漫画を伝える人々」を映画化したもので、監督は数々のドキュメンタリー番組を手がけ、本作が映画初監督となった込山正徳さん。『香川1区』『国葬の日』の大島新さん、『NO 選挙,NO LIFE』の前田亜紀さんが共同プロデューサーとして参加している。
横浜出身の込山監督は、漫画を読む習慣がなかったことから、『はだしのゲン』についてはほぼ知らなかった。だが、昨今の『はだしのゲン』をめぐることはニュースで見ながら「変な流れだな」と思い、初めて『はだしのゲン』を読み「インパクトがすごい。この熱量はすごい」と気づき「これは世の中に知らせなきゃいけない」と確信。「『アンネの日記』は、ユダヤ人差別を子ども目線で描き、戦争について分かる日記ですよね。 『はだしのゲン』も子ども目線で、広島の原爆の下で何が起こっていたか、を記録した作品。世界に通用する文学なんじゃないか」と思わされ「逆風が吹いている今こそ、なにかを企画しなければ…ドキュメンタリーのテーマにすればいいんじゃないか」と着想し、企画した。
そこで、取材先を検討していく中で講談師の神田香織さんを発見。「『はだしのゲン』に関する講談を40年近く続けている人がいるんだ」と驚き「『はだしのゲンを読んだことがない人にも分かるようになる」と閃いた。また「作中には、漫画も貼り付けると分かりやすくなる。まずはそういったシーンを作ることが出来るな」と思い、最初の流れを作っていった。そして、『はだしのゲン』に対する批判へ牽制するべく「作品に出てきた人達と同じような経験をしている方を探し、証言を加えることで説得力を持つ」と考え、相応しい方をインターネット上や書物から探していく。そこで、江種祐司さんや阿部静子さんに取材することが実現。既に高齢であるため取材時間は限られたが「戦争を体験し被爆した方々が伝え残したい意思の力がすごい」と手応えを感じられた。『はだしのゲン』に対しては肯定的に受けとめられており「原爆を落とされてからの1ヶ月、その時に何が起こっていたのか、が漫画には克明に描かれており、それらが本当であることを証明できた」と込山監督は捉えている。
取材後、BS12スペシャル「『はだしのゲン』の熱伝導 原爆漫画を伝える人々」として放送されたが、45分の番組であり、伝えられる内容には限界があった。映画化を考えていた中で、知り合いから「『はだしのゲン』をよく思わない人の意見も聞きたい。何故これが排斥されているのか知りたい。そこを詰めてほしい」と言われ、批判派の意見を盛り込むことを検討。様々に調べていく中で、後藤寿一さんの書籍「『はだしのゲン』を読んでみた」を行きつき、実際に読んでみると「『はだしのゲン』にはインチキが混じっている、といったことが書かれている。じゃあ取材してみたらいいかな」と考え、オファーしてみることに。取材に応じてもらい、インタビューしてみたが「歴史認識等は、僕とはかなり違っていた。ただ、そういった考えを持つ方も日本にかなりいる。そういった論理で展開したら『はだしのゲン』は論理がおかしい、と思うところもあるんだな。この問題を考えてもらうきっかけになるだろうか」と『はだしのゲン』への逆風を受けとめた。その数日後、1991年より広島市⻑を8年間務めた平岡敬さんのインタビューをしており「私自身が勉強しなければいけない歴史認識、日本がどうして戦争に突き進んだのか、等について質問し、端的に応えていただき、分かりやすかった」と納得している。また、腹話術の⼈形を3歳で被爆し亡くなった弟に⾒たて、⾃⾝の被爆体験と平和の尊さを伝える活動を続けている⼩⾕孝⼦さんは頻繁に様々な学校で講演を行っており、学校や教育委員会に取材協力をお願いしたが、 悉く断られてしまった。そこで講演を聞きたい子ども達と親御さんを集めることに。当日に集った子ども達を撮ることができ「表情など全て撮れたのが幸運だった。 講演会の終了後、子ども達と小谷さんが会話しながら、『はだしのゲン』が子ども達に浸透していく様子が撮れたので良かったな」と安堵している。
編集段階となり「撮った素材をどのように並べればいいか…思い浮かぶんですよね。コレとコレをこんな風にしよう、とか、このコメントはこの後に使おう、とか色々考えながらやったんですね」と思い返す。個別のシーンについて、ナレーションを入れたり、同時録音によるインタビューのコメント入れたりと吟味しており「どのように構築していけば、この強い言葉が活かせるのか、という考え方で編集するんですよね。テレビドキュメンタリーを40年ぐらい作っているのでノウハウがあるんですよね」と自信があるが「私、63歳にして今回が初監督であり、テレビと映画は全然違うので、手探り状態でした」と告白。とはいえ「映画だったら、余白を作った方がいいんじゃないかな」と考え「テレビ番組は、人に考えさせる余裕がなく、テロップもしっかりと入れていく。 分かりやすさを意識するのがテレビ番組の作り方。それを少しだけ緩くするなら、映画は説明過多じゃなくてもいいのか」と意識し、他のスタッフの意見も取り入れて仕上げていった。
完成した作品を以て試写を行った際、舞台挨拶も実施しており「拍手をいただきましたが、泣いた後の人たちが多かったな。目を腫らしたり、クスンクスンとしていたりする方が結構おり、伝わったのかな」と受けとめている。そして「こういうことを伝えていかなきゃいけないですね」といったポジティブな意見を多くいただいた。今後は、欧米諸国での上映も視野に入れており「原子爆弾の下でどんなことが起きていたのか、を知ってもらいたい。『はだしのゲン』が25ヶ国で翻訳出版されているので、お客さんの下地も多少なりともあるかもしれない。映画『オッペンハイマー』で描かれなかった部分を、本作を観て分かってほしい」と意気込んでいる。「現在、アメリカの若者たちの中では、原子爆弾は間違いだった、と考えている方のパーセンテージが少しずつ上がっているんですよね。 だから、何が起こっていたのか、現実が分かってくると、皆が変わっていくんじゃないかな」と期待しており「世界中の方にも観てもらいたい。核がそれでもなくなっていかないことについて、皆に考えてほしいですよね」と訴えた。
映画『はだしのゲンはまだ怒っている』は、関西では、11月21日(金)より京都・烏丸の京都シネマ、11月22日(土)より大阪・十三の第七藝術劇場や神戸・元町の元町映画館で公開。

- キネ坊主
- 映画ライター
- 映画館で年間500本以上の作品を鑑賞する映画ライター。
- 現在はオウンドメディア「キネ坊主」を中心に執筆。
- 最新のイベントレポート、インタビュー、コラム、ニュースなど、映画に関する多彩なコンテンツをお伝えします!